煮もの(NIMONO)

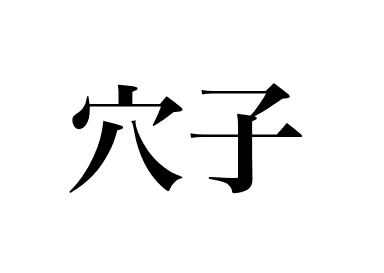
穴子の握り
【握り寿司: 煮物】火を通し、甘みのある煮ツメを塗って食べる。握り寿司の中でも別枠の味わいがあり、人気のネタなのが、穴子。そのため寿司屋の中には、一年を通して、同じ太さ、同じ大きさの物を仕入れ、味に差が出てないように気を配る所もある。
寿司ネタとして使われるのは、ウナギ目穴子科の真穴子。昔から「穴子は江戸前に限る」と言われるように、今でも羽田沖の穴子は上物とされているが、数が少なく、あまり出荷されないのが実情。しかし、羽田沖以外の神奈川県金沢八景や小柴、千葉県木更津、富津などの東京湾の物も味はいい。穴子自体は北海道以南の日本全国に分布している。長崎県対馬や瀬戸内海でもよく獲れ、近年は韓国や中国からの輸入物も多い。
一年を通して美味しく味わえるネタだが、特に脂のって旨いとされるのが、6~7月。梅雨により川から養分が海中に流れ込み、それによって餌が増えるため、さらに美味しくなるという。ただこれは東京湾の江戸前の穴子の旬です。かつては東京の名店の多くが江戸前の穴子を使っていました。でも漁獲が減り品質にムラが出るようになったため、今は長崎県対馬産の穴子を使うようになっています。対馬の穴子の漁場は水深が深く水温が安定していて、季節によって品質があまり変わらないため使いやすいのです。また関西の寿司屋では、焼き穴子を握る一方、関東では煮穴子を握るのが一般的になっているというのも面白い。
江戸前寿司の元祖、華屋與兵衛が店を出した時には、寿司ネタとして蛤や車海老と共に、煮物として穴子が加えられていたという。このように江戸前寿司の初めからネタとして使われていたのだから、今もその仕込みには細心の注意が払われ、それゆえ店それぞれの味の違いが生まれている。
江戸前寿司を代表するネタの一つだ。梅雨から夏にかけて、濃厚な脂がのってくる。煮上がった穴子を口に入れればふんわりとろけ、上質な脂がやさしく舌を包み込む。塩で食べるもよし、甘いツメで食べるもよし。
体の真ん中にあるヘソ(肛門)を境界に頭を上(かみ)、尾の方を下(しも)という。脂ののりは上の方が強い。昔はよく動かすから下の方がうまいというのだが、これはどうか?!
そして「上は皮表、下は身表」とよくいわれる。皮表とは皮目の方を上にして握ること。身表とは身の側を上にして握ることを指す。穴子は煮ると身ワレが出来がちで、その割れ目に煮ツメが入り、見た目が悪くなることがある。しかし身によほど割れ目が入っていない限り、上も下も、身表に握ることが多い。
分類:ウナギ目アナゴ科クロアナゴ属
学名:Conger myriaster
地方名:トオヘイ(大分県)、ホシアナゴ(兵庫県)、ハカリメ(関東、和歌山県)、カリメ(関東、神奈川県)、トヘイ(千葉県)、ヨネズ(富山県)、タチウヲクラゲ(紀州)、ゴマ(山口県)、ビリス、ドテダオシ(鹿児島県)、ハモ(北海道、東北地方、山陰地方)、ホンアナゴ(神奈川県)、メジロ(三重県、名古屋)、メバチ(高知県)、ベースケ(伊予)、ハム、ドグラ(有明海)
魚名の由来:日中、岩穴や砂の中に、身を潜める生態から、その名が付いた。

